
良質な土をいまに残し・伝える器 – 備前焼2025.03.11

第七回目となる今回のジャーナルでは、皆さまにお召し上がりいただく食事を彩る器の作り手をご紹介したいと思います。食材を盛り付ける器は、私たちの食体験に欠かせない大きな要素のひとつで、撚る屋では歴史ある「備前焼」の窯元、「陶工房斿」さんと「一陽窯」さんの食器をいくつか使用させて頂いております。今回はお二組の窯元を伺い、様々なお話を聞いてきました。

「備前焼」は、日本を代表する古窯として「六古窯」のひとつに数えられる歴史ある産地です。古墳時代に「須恵器」と呼ばれる土器が作られるようになったことを始まりとし、平安〜鎌倉時代までは食器や瓦を中心に、室町時代からは茶道の発展と共に茶陶が盛んに作られてきました。江戸時代に入ると磁器の台頭により一時衰退しますが、明治時代に入り「備前六姓」に数えられる名家 金重家に生まれた、金重 陶陽(かねしげ とうよう)が、優れた陶工として名声を高め、それまでの備前焼にはなかった造形性の高い表現を次々と生み出します。
そんな陶陽の弟で、茶陶の第一人者と呼ばれた金重 素山の嫡子、金重 有邦を父に持ち、備前焼の魅力を今に伝えているのが、「陶工房 斿」の、金重 周作さん、陽作さんのご兄弟です。
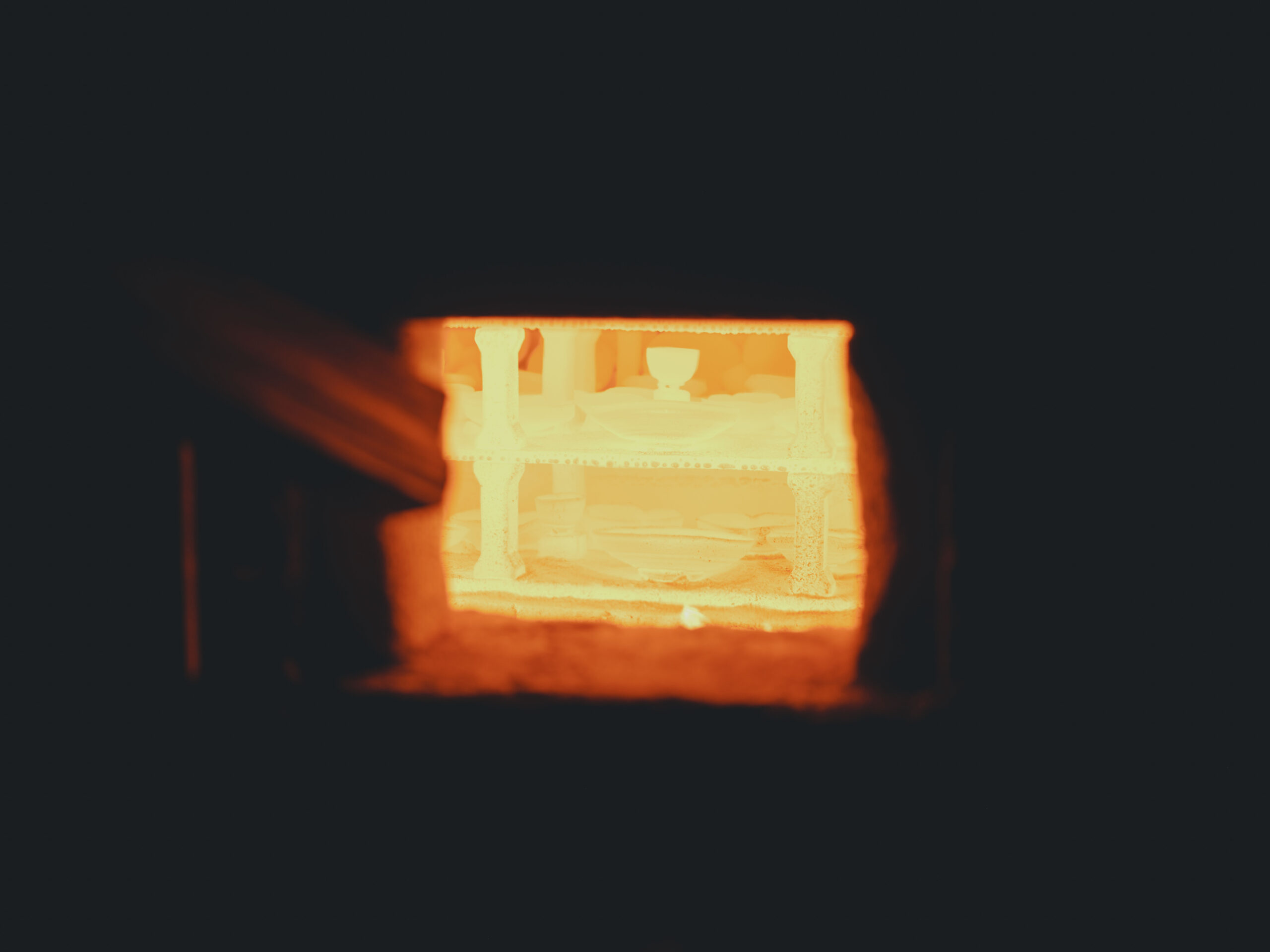
屋号として掲げられている「斿」という漢字は、祖父が作った茶室の号である「ゆう庵」(ゆうの字は、“手偏”に“遊”と書く)から、いただいたものだと言います。しかし、パソコンで入力ができなかったので、同じ読みの「斿」という一字が選ばれました。この漢字には“旗のしたに集いあそぶ”という意味があり、工房の屋根の下、皆が集って作陶をしているイメージと重なった為、この屋号としたのだそうです。取材の中でも、ご兄弟の仲の良さがとても伝わってきました。

作陶におけるこだわりをお聞きすると、「焼き物を知らない人に、焼き物の魅力を伝えるのが使命です」とお話しくださいました。茶席や懐石の場で用いられる茶陶は、敷居が高く、難しいものに見られがちです。“良い器”とはどのようなものなのでしょう?との問いかけに、「大切なのは、お茶やお料理を盛られている姿が美しいかどうかです。亭主のもてなしの心を盛り付けることができる器が、良い器なんです。」そう教えてくださいました。
撚る屋では、ご夕食の際にお二人の作られた「向付」を使用しています一般的にはカクカクとした形であることが多い向付ですが、お二人は備前の土の特徴を活かした曲線を取り入れることを意識されたそうです。
素朴で無骨、ぽってりしていると言われることがある備前の土、お二人はその特徴を「手に吸い付いてくるような瑞々しさ」であると言います。そして、柔らかさの残る艶を残したまま焼きあがることが、一番美しいのだと言います。お二人の向付に現れているしなやかな曲線には、備前の土が持つ瑞々しくしなやかな魅力がありありと現れています。

続いてお話を伺ったのは、金重家と同じく「備前六姓」に数えられ、室町時代から続く名家、木村家の分家、「一陽窯(いちようがま)」の3代目 木村 肇(きむら はじめ)さんです。

肇さんは、窯元の息子として、職人達が働き、自宅の玄関は作品を並べたお店という環境の中で文字通り備前焼と共に育ちます。小さなころ最初に教わったのは、備前焼の命とも言える「土」作りだったと言います。

日本を代表する陶芸家 北大路魯山人は、「備前の土は、世界一」と評しましたが、釉薬をかけない焼き締め陶である備前焼は、その土質の良さを最大限に活かす技術で、高い評価を誇ってきました。
肇さんは「人の作った粘土で轆轤をしても気持ちが入らない」と言い、「自己表現のために粘土を焼くことをいいとは思わない」と、はっきりと仰います。そして、「人の役に立つもの、用があるものを作りたい。自分で練った土に触れていると、自然とそういう気持ちになるんです」とお話しくださいました。

撚る屋では、ご夕食の際に「高台」を使用させて頂いております。一見するとシンプルな円柱の器ですが、細かなところにこだわりが込められています。裏返すと筒状になっており、食材を盛る平らな部分は「器の裏」にあたります。しかし、器の裏であれば、轆轤から離す際に特有の加工跡が残り、一眼で器が「裏」を向いていると感じてしまいますが、肇さんの高台は、器の表と同じようなしっとりとした備前特有の表情を有しております。加えて「縁」を僅かに反り上げてあるので、料理を盛った際に、きちんと食材を受け止める器の「表」の表情を見せており、料理への深い理解がなければ作ることの出来ない、大変美しい仕事です。

肇さんも周作さん、陽作さんも皆さん口を揃えて、「備前焼は、土の恩恵で続いてきた」と謙虚に仰っていたことが印象的でした。粘土を思いのままの形に作るのではなく、粘土の中から粘土の成りたい形を見つけているかのような作品からは、豊かな備前の土の包容力をそのまま感じられます。

美味しい料理に、豊かな食材が不可欠なように、美しい器には、豊かな原料が不可欠だと思います。撚る屋にお泊まりの際は、土に生かされ、伝統に生かされる、備前焼の現在そして未来を担う陶芸家の作品の魅力を、お料理と一緒にどうぞお楽しみください。

撚る屋 上沼佑也、ライター 朝倉圭一














